無色の死
メヒディ・メクラとバドゥルディーン(以下バドゥル)・アブダラは、実存主義のアイコンからフランスを代表するカリスマ歌手へと転身を遂げたジュリエット・グレコとお茶をするため、席についた。
午後の光。寒空は美しい白さをたたえていた。すべてのものから遠く離れ、風が吹き抜ける、忘れ去られた石造りの村。一日が終わろうとする頃には教会の鐘が鳴り、凍てついた魂を驚かせる。タクシーの運転手は言う「こんなところまでわざわざ来る理由はひとつしかない。ジュリエット・グレコに会うためだ」。扉を開けたジュリエットは、肩に黒いショールをかけ、その顔はあまりにも青白い。テーブルにはiPhoneといくつかの化粧品、そして紅茶が入ったカップが3つ置いてある。大音量でテレビがついている。「この人って……」ジュリエットはスイッチを切る。暖炉で燃えている炎がのんびりとはじける。ジュリエット・グレコは白黒のアイコンである。限界を知らないその瞳は切実に自由を求める。ジュリエットは言う「私のことなんて誰も知らないわ」。86歳の彼女は、数多くのことを経験してきた。「命について言うなら、私はその限界に立ち向かっていると言えるわね」とジュリエット。これは、とある会話である。
ある日突然、あなたはジュリエット・グレコになったわけですね?
私はジュリエット・グレコです。私はそのように生まれてきました。これが私の名前。ジュリエットは私の名前。問題は、私が選ばれたということ。もし選べたなら、どんなことがあっても自分を選ぶようなことはしないわ。私は醜いし、これは一生変わらない。私は自分の身体的な特徴が本当に嫌いでした。コンプレックスの塊ね。戦争のあと、サン=ジェルマン=デ=プレは瞬く間に世界中の才能あふれる人々が集まる‘るつぼ’になりました。当然ながら、写真家たちもあふれていました。だって才能があるところには決まって被写体となる才能の持ち主がいるから。私もそこにいました。「あの人がジュリエット・グレコだ。彼女がここで起きていることのシンボルだ。彼女にはそれにふさわしい顔つき、服装、無頓着さ、奇抜さがある」写真家のウィリー・リゾやほかの人々の評判が伝わっていったようです。
誰もが予見していたことを、あなただけが見抜けなかったのでしょうか?
そうではありません。私は自分のことを汚くて醜いと思っていました。そして運命的な恋をしていました。演劇の世界を生きたいと願う、熱烈な悲劇俳優だったのです。歌うことについては何も知りませんでした。もうおわかりでしょう? 風変わりなひとりぼっちの人間だったのです。でも、ひょっとして私が選ばれたのは、ほかの人と違ったからかもしれません。私は孤独を感じていました。
でもあなたの優しそうな瞳は、自分自身を愛するのに役に立ったでしょう?
ずっとあとになってからですね。それまでは、自分の身に何が起きているのか、理解することなんてできませんでした。すばらしい人々に出会いました。私なんて何者でもありません。私は、ただの私でした。でも、社会的には許容されない存在でした。なぜなら、私は少年のような黒い服に身を包んだ、物静かでひとりぼっちの変わり者だったから。でも、黙っていないときは、どちらかと言えば乱暴な、野生児でした……
Mais ce beau regard, d'eux sur vous, vous a aidé à vous aimer?
Bien longtemps après. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'étais rien. Enfin, j'étais moi. Mais socialement, j'étais irrecevable, parce que j'étais bizarre :
Un être seul, habillé de noir, comme un garçon, muette, et quand pas muette assez violente, sauvage…
野生児」とはどういう意味でしょう?
3歳の頃、正面玄関の階段から祖母がメードを投げ飛ばすのを見ました。わけがわかりませんでした。メードの女性はとても美人だった。でも彼女はポルトガル人だったのです。大きな緑色の瞳と黒いお団子頭。19歳で、まだ少女でした。まさに奴隷です。これも理解できませんでした。それでも、私は私。いつも戦闘状態……でも周りにはすごく迷惑かもしれません。だって3歳だった私もいまは86歳になって、それでもまだ戦い続けているのですから。
あなたは「野生児」で「風変わり」で黒ずくめだった……はじめて色の神秘に惹かれはじめたのはいつからですか?
収容所から釈放されてからです。私は、自分という存在ゆえに収容所に入れられました【註:レジスタンス活動に参加したことで母と姉とともにヴァル=ド=マルヌ県フレンヌの収容所に収容、年齢的な理由でジュリエットだけが解放された】。16歳のときです。当時は下宿をしていました。洋服なんて、バッグに入っているものしか持っていなかった。それは姉のジャケットとラフィアの靴でした。当時は革靴なんてなかったから。男の子たちは私のことを憐れに思ったのか、いらなくなったジャケットやパンツをくれました。私は背が低かったので、パンツの裾を足首までロールアップして履いていました。本当に不愉快な子どもでした。好きな人は好き、嫌いな人は嫌い。私は自分の本能を疑ったりはしないので、まさに野生の獣でした。
黒という色があなたの人生に意味を持ちはじめたのはこの頃からですか?
私は男の子の服装をしていました。それが終わり、はじめて自分でお金を稼ぐようになってから買ったのが黒いパンツと黒いプルオーバーでした。人に気づかれることもなく、透明になったような快感をおぼえました。
まさに鎧ですね。
そう、鎧でした。はじめて日本を訪れたとき、なぜいつも黒い服を着るのか、と日本の方に訊かれたことがあります。「自分が透明になった気分になれるから」と答えました。するとその人たちは言いました、黒は守りの色だと。それはさておき、私が世界でもっとも好きな画家はあの豊かな色彩を生み出したヴァン・ゴッホなのです。色はぬくもりをもたらしてくれます。気分を良くしてくれるのです。私をなぐさめてもくれますが、私には似合いません。
それだけでなく、すでにあなたは独特のアイメイクをしていました。おまけに黒髪でしたね。
収容所から出ると、ほかの女の子たちと同じようにメイクをしました。黒いアイライナーを何本か買って、のちに人々が「ドウ・アイ(くりくりとした愛らしい眼)」と呼んだアイメイクを発明したのです。ほんと、バカよね、億万長者になれたかもしれないのに…… 自分の眼の形からアイディアを得たのです。エジプト人みたいに切れ長の眼をしていたから…… 別に意図的にやったわけではありません。私のなかから自然と沸き起こったものです。それ以来、私の武器は少しのマスカラとパウダー、そして黒いアイライナーペンシルです。
 |
「私の武器は少しのマスカラとパウダー、そして黒いアイライナーペンシルです」 |
黒は決して絶望の色ではなかったということでしょうか?
黒という色は存在しません。黒は青、紫、赤です。絶望の色とは、色が存在していないことです。もしかしたら、色を見ないことが絶望の色なのかもしれません。
「黒の画家」として知られるスーラージュの作品にも絶望はない、ということですね?
その通りです。スーラージュの作品には無数の反射が描かれています。それはとてもダイナミックです。白にも同じことが言えますね。「真っ白」というものは存在しません。本当のこと言えば、唯一、サウジアラビアにはありますね。男性がみんな白装束だから。白という色は深遠な色なのです。どうしてって思いますよね? だって白は限りなく華やかで、とても美しいから。アラブの人の白はすばらしいですね。あのようなものを、私はいままで見たことがありません。
黒は抑圧の色である、とも言いますね?
でも、黒人の人々はどうなるの? 黒人の男性も女性もとても美しいと思わない? それに黒人と言ってもみんな黒さの度合いが違うから、真っ黒とは言えませんね。黒い肌を見極めるのは難しいことです。それに対して、白い肌は簡単。たとえば、ノルウェーはピンク色ですし、もっと南の人はやや青みがかった薄い色をしています。これが世界です。どのようにして私たちが白人になったのかは知りたいところですね。だって私が知っているかぎり、人間というものは当初はみんな黒人だったのですから。




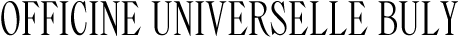

laissez un commentaire
Connectez-vous pour poster des commentaires